学術知共創プロジェクトマネージャー・堂目卓生(大阪大学社会ソリューションイニシアティブ長・大学院経済学研究科教授)と、人文学・社会科学の研究者を中心とした人びととの対話から、人文学・社会科学が社会に果たすべき役割、共創の場を創るヒントを模索します。
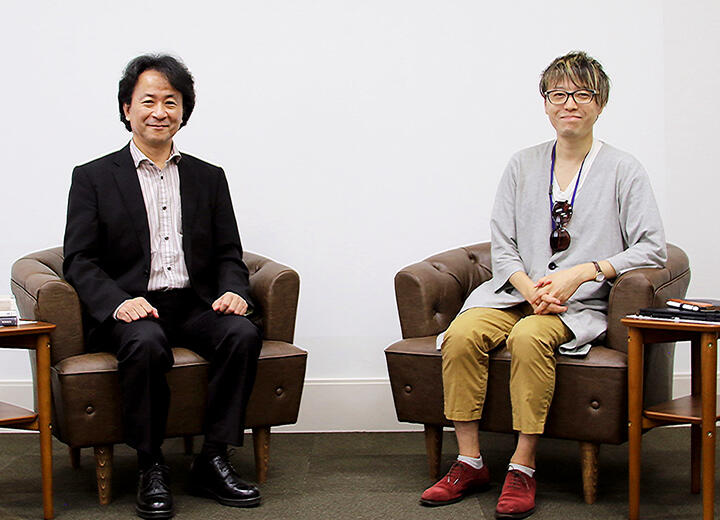
◆今回の対談テーマ
「 知識生産が真に社会的脆弱性(ヴァルネラビリティ)を解消する行為であるために 」
◆今回の対談者の紹介
気候変動、エネルギーの枯渇、貧困、感染症、紛争等による災禍は、社会の中の脆弱な階層、いわゆる「弱者」(ヴァルネラブル)に最も深刻な打撃を与えます。社会課題に向き合い、解決の糸口を探る中で、私たちは「弱者」に対する眼差しを忘れてはなりません。社会課題の解決とは社会的脆弱性の解消にあると言ってもよいでしょう。こうした視点から、今回は、「脆弱性」(ヴァルネラビリティ)の解消という視点から科学技術のガバナンスのあり方を探りつつ、災禍の中にある人びとが語る声に耳を傾け、さらには声なき声をも形にしようとされている標葉先生に、学術と社会の良い関係とはいかなるものかについて、お話しいただきました。

標葉隆馬 大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)准教授
1982年生まれ。京都大学農学部応用生命科学科卒業、京都大学大学院生命科学研究科博士課程修了(生命文化学分野)。博士(生命科学)。総合研究大学院大学先導科学研究科「科学と社会」分野 助教、成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科 准教授などを経て、2020年4月より現職。専門は、科学社会学・科学技術社会論・科学技術政策論。最近の著書に『責任ある科学技術ガバナンス概論』(ナカニシヤ出版 2020)、『災禍をめぐる「記憶」と「語り」』(ナカニシヤ出版 2021)など。
先端科学と人文学との二足の草鞋(わらじ)を履いた学部時代
堂目 標葉先生のご専門は科学社会学、科学技術社会論、科学技術政策ですが、博士号は生命科学の分野で取られています。また著書を拝見すると、専門領域に留まらず幅広い領域に関心をお持ちのようです。そのあたりも含め、これまでのプロフィールをおうかがいできればと思います。
標葉 私は、農学部出身でバイオテクノロジーや遺伝子組換えを実際に行うような学科で学びました。ただ高校時代にはカントなどドイツ哲学にはまったりして、生物か哲学か迷いながら大学に入ったんです。1回生の時、一般教養の授業で宗教人類学の授業を受け、非常に充実した参考文献リストをもらいました。リストに沿って、宗教学のミルチャ・エリアーデ、文化人類学のレヴィ=ストロースやヴィクター・ターナー、社会学のエミール・デュルケームなどの文献を読み始めたところ、とても面白くなりまして。農学部で学びながら、そういった人文社会学系、特に社会学や人類学の古典を一人で読みあさる二足の草鞋みたいな生活をしていました。大学院に進学する時、折角両方やってきたので、科学という社会現象や人の営みを社会科学や人文学の視点から分析・理解していこうと、今のジャンルに決めたのです。博士号も、今の研究分野と同じ、生命科学の社会的課題や倫理的課題で取りました。なので、博士(生命科学)ですが、あくまで「生命科学の社会的課題」に関する博士号ですね。

堂目 二足の草鞋の学部時代に、経済学者アマルティア・センの著作にも触れられたそうですね。
標葉 大学生協の書店で偶然見つけ、邦訳されているものを一通り読んでいきました。ケイパビリティ、あるいは選択肢を増やすことの重要性、それに対する公教育の寄与など面白い視点がたくさんあって、すっかり感化されました。『貧困と飢餓』では、食糧の分配システムの欠陥によって多くの人が死ぬという飢饉の現実が、非常に鋭利に書かれていることに衝撃を受けました。また、ポストコロニアル研究のエドワード・サイードにも影響を受けました。知識人や学者のふるまいをメタ的に見る視点やその規範といった議論は、今でもかなり意識しています。
科学技術に必要なガバナンスとは
堂目 それでは、専門分野のお話をうかがっていきたいと思います。科学技術は社会的文脈の中から出てくるものですし、科学技術が社会を変えていく側面もあると思いますが、標葉先生は、どのような視点から科学技術と社会の関係を捉えようとしているのでしょうか。
標葉 科学技術はまさしく人の営みであり、社会と不可分な関係にあると思います。人の営みだからこそ、そこには色々な局面で価値観や規範をめぐる問題が必ず出てきます。それがどのようなものなのかを詳らかにしていくことが非常に重要です。そのうえで、科学技術と社会とのより良い関係とはどういうものか、より良い関係性をどうやったらつくっていけるのかを考えていく。より良い関係を構築するために、より上流から適用できて、かつボトムアップでいろんな意見や価値観を包摂していくようなガバナンスのあり方とは何か、という問題に関心を持っています。
堂目 そのような研究の蓄積を著書『責任ある科学技術ガバナンス概論』にまとめられました。そのポイントをお話いただけますか。
標葉 科学技術は、多くのベネフィットを私たちにもたらすとともに、時に社会的な問題や対立も生み出してきました。そうした歴史の教訓に根ざして次の議論をするのは当たり前のことですが、必ずしもそうなってはいません。科学政策がつくられるとき、教訓も含めた重要な論点が取りこぼされたり、顧みられなかったりすることが往々にして起こります。そうではなくて、過去の知見蓄積に依拠した議論がまず必要だろうし、そこで得られた教訓に基づいて次のガバナンスのあり方を考えていくことが、今後のより良いイノベーション・エコシステムの土台作りの最低限のラインではないか、というような趣旨です。
堂目 ガバナンスというのは、誰のガバナンスなのでしょうか。政府、科学者自身、あるいは科学技術の影響を受ける人ですか。
標葉 国際的なもの、国内のもの、さらに科学者のコミュニティなど、様々なレベルがあると思います。科学者のコミュニティは国内だけに留まらず国際的なネットワークを築いていますから、また違うものになるでしょう。そういったレベルごとに、重要な知見や守られるべき規範や指針の形成など多様なガバナンスがありますが、それらは連動しているため、全部を総体として捉えるガバナンスのあり方が大事だと思っています。
科学技術、もっと広く言えば知識生産は、社会や人の影響を受け、また逆に影響を与えながら進んでいきます。いろんな価値観や意見を可視化し包摂し、多様な知見や意見の往還をする、そのようなダイナミクスの中で、知識生産と社会のより良い関係を構築していく。そういう意味でガバナンスという言葉を使っています。

堂目 なるほど。そうすると、そのレベル間、組織間のコミュニケーションがうまくできるのかが重要になりますね。特に、科学技術を市民がどう受け止めるか。ゲノム編集であれAIであれ、開発する側は、研究者自身の考えや使われる現場での見方をガバナンスしているつもりでいても、市民はそれを全然知らないこともあり得ます。
標葉 様々な意見や価値観、問題の捉え方があり、その多様性をどれだけ可視化、共有できるかが、最初のステップとしてとても重要だと思います。研究や実践を通じて可視化された多様性を共有し、何を議論するべきなのか、どういう価値観や規範に立脚して問題を捉えるかという議論を進めていいかなければならないと思います。
ガバナンス構築の国際競争に出遅れる日本
堂目 科学技術と社会の関係や、組織同士のコミュニケーションについて、日本は他国に比べてうまくいっているのでしょうか。
標葉 難しい質問ですね(笑)。日本に限らずどこも苦労しているのは確かで、むしろ、より良いガバナンスやプロセスの形成自体が国際的な競争になっているのが現実でしょう。その中で日本は出遅れているのではないかと個人的には思っています。
堂目 社会と知識生産をうまく繋いでいく競争ですか。社会に知らせないで進めたほうが、科学技術だけの進歩を競う競争には勝ちそうですが。
標葉 短期的に見れば、知らせないでどんどんやってしまった方が進展する可能性は高いかもしれません。しかし、中長期の視点では、社会や人々の価値観とかけ離れていたり、受け入れる準備ができていないといったリスクがより大きくなると理解されていると思います。新しい知識が社会の中に根付いていく際には、より早い段階から、様々な受け止められ方や価値観を把握しながら一つずつ進めていく方が、結果として速く、トータルコストも低くなる。
ELSI(倫理的・法的・社会的課題)の議論も含め、ガバナンスとその構築プロセスのスタンダードを獲得、さらには価値の次元まで踏み込んだ社会的議論の競争が国際的に行われているという意識は、日本にはまだあまり根付いていません。そのような現状に、危機感を抱いています。
堂目 日本の科学技術政策についてうかがっていきます。日本の科学技術政策の基本的な枠組みを定めた科学技術基本法が、2021年4月に改正されました。名称も「科学技術・イノベーション基本法」へと変わり、それまでは含まれていなかった人文科学も含んだ形になりました。この動きは、今おっしゃった体制やガバナンス構築プロセスの国際競争に日本が追い付いていない、という中で出てきたのでしょうか。

標葉 科学技術・イノベーション基本法について語るには、その歴史的な経緯を踏まえる必要があります。日本では、科学技術・イノベーション政策と言われるものが、歴史的に、経済的な成長戦略の下位戦略として位置づけられてきました。その中で、イノベーションという言葉がものすごく狭い意味、経済成長をもたらす技術的なブレイクスルーといった、かなり限定的な意味で使われてきました。一応、改正法の本文には、イノベーションの意味をそのように狭くしないようにしようという努力の跡が見られますが・・・。従来の限定的な使われ方、構造的な問題をいかに解消し、より良い、開かれた意味でのイノベーションにつなげていくか。そこに、人文学・社会科学の第一の役割があると思います。
堂目 人文学・社会科学にそのような要請がある、と受け取ってしまっていいような気もしますが。
標葉 受け取ったことにして、やるほうがいいというか(笑)。少なくとも、我々学者の側がこの変化をどういう機会として捉え、どのような言論を展開していくのかが大事だと思います。
堂目 人文学・社会科学の役割は、イノベーション、社会変革の意味を様々な視点から広げていくことだと。他方、自然科学では、イノベーションを技術革新というようなもっと狭い意味に捉えがちだということでしょうか。
標葉 例えば最近の欧州の政策文書などを見ていると、自然科学を含めた研究者のコミュニティ自体が、もっと価値の議論に踏み込んで発信していかなければならないとはっきり書いてあるものもあります。知識生産が社会とつながり、いろんな知識が社会に根付いていくということが重要視され、そのプロセス自体が競争になっている中で、価値をめぐる議論の積極的な発信が、研究者コミュニティ全体に求められるようになってきています。日本もそうした流れに乗るのがいいかどうかは、本当はちょっと議論がいるかもしれません。しかし、やらないで外から来る議論に乗るしかなくなるよりは、より良い形で価値の議論の発信を模索することが必要だろうと思います。
災禍の研究とヴァルネラビリティ
堂目 価値というお話が出ましたが、標葉先生にとって、ありたい社会、めざすべき社会とはどのようなものなのでしょう。また、その実現のために解決しなければならない社会課題をどう考えますか。2012年に『災害弱者と情報弱者:3.11後、何が見過ごされたのか』、8年後の今年には『災禍をめぐる「記憶」と「語り」』を出版されていますが、専門である科学技術と社会の関係と災害・防災への関心がどのように結びついているのかも含めてお話いただけるでしょうか。
標葉 災害・防災のテーマを始めることになったのは、東日本大震災が地元で起きたというのが一番大きな理由です。高校まで住んでいたのが宮城県仙台市で、もともとのルーツは福島県の浪江町です。浪江町にあった祖父の家は震災に遭って崩れ、避難指示区域になったために入れなくなってさらに崩れ、最後は更地になりました。科学技術と社会をテーマに研究している中で、震災によって実際に自分のプライベートも含めて様々な影響を受け、3.11はとても無視できるものではありませんでした。やる以上はライフワークになると思いながら、3.11翌日から研究をスタートしました。ずっと使ってきた、メディアの定量的な解析や社会的なデータの分析をスタート地点として、まずできることをやろうと考えました。「この災害がどのように語られるのか」を考えるための粗くてもいいからまず基礎データを取る目的で行った研究をまとめたのが、2012年に出版した本です。
ただ、それだけでは見えないものもたくさんありました。震災直後には言えなかったこと、あるいは語り手自身、表現する言葉が見つからなかったことがたくさんある。長年テーマに関わる中で、そのような語りの可能性のプールというか、「語られるかもしれないこと」というのが、実は、災禍を考える上ではより重要なのではないかと強く感じるようになり、それが最近出した本につながりました。今語られて言葉、形になっているものも大事ですが、言葉になるかもしれないこと-その方が当然より多くあるわけですが-それらがいかに形になりうるのかも大切なのではないかと考えています。
災禍の研究を通じて、社会的脆弱性、ヴァルネラビリティ(vulnerability)という視点の重要性を思い知りました。先ほどの問いにあった、めざす社会像ということで言えば、ヴァルネラビリティがより解消されていく社会こそがよい社会だと思っています。それは格差の解消や多様性への理解の向上、あるいは差別が無くなるといったことも含んでいます。
ヴァルネラビリティの解消に対して、知識生産、つまり科学や人文学は、どのように貢献し得るのか、本当は解消にもっと貢献し得るはずなのにそれができていないとすれば、どのような仕掛けがあれば良いのか。そのような問題意識から、より良いガバナンスのあり方の追求が重要だと思うようになりました。知識はその使い方によっては、特定の人のヴァルネラビリティを増やしたり、新しいヴァルネラビリティを生み出したりしてしまう。それを防ぎ、既存のヴァルネラビリティをより減らすための知識の使い方を考えることがガバナンスにつながります。

語りや語りの可能性を丁寧に拾い集める
堂目 数値化できるデータから、語りというエピソードそのものへ、さらにはエピソードになっていないものにまで研究対象を広げていこうとされています。その理由は、どういうところにあるのでしょうか。
標葉 まず、定量的な分析と定性的な分析は相補的なもので、どちらが欠けてもいけないと思います。その中で、数字というものは様々な文脈を削ぎ落とすことにもなるため、いろんなエピソードが見えなくなります。その意味で、数字にすることには暴力的な側面もあると思っています。しかしながら数字として削ぎ落すからこそ浮き彫りになる構造的問題を見る視点と、今は表現されていない、でも表現され得るかもしれないものも含めて見ていく視点とを両立させていかないと、脆弱性の解消という行為自体が矮小化してしまうのではという危機感があります。
堂目 日本語の「かたり」には、その人が話すという意味と、嘘を言うという意味がありますね。語られなかったことのほうにむしろ真実性があったり、生きていくために記憶さえ変えて、そうであったことにする、といったこともあるかもしれません。フィールドワークでは、どんな感触がありましたか。
標葉 少なくとも、その人が、そのように語った、という事実がまず重要だと思います。仮にそれが、いわゆるファクト(fact)みたいなものと少しずれていたとしてもです。語りが表れてこないことには、出来事を取り巻く多様なリアリティには漸近すらできないでしょう。また、語りを様々な他のデータや調査などと引き合わせて見ていくことで、よりビビッドにリアリティが見えてくることもあります。語りの可能性を丁寧に拾い集め、現場をとりまく状況とコンテクストを理解し、リアリティを直視することが、ヴァルネラビリティの解消・軽減という社会的価値の実現に繋がるのだと思います。またその際ポストコロニアル研究の知見、特にガヤトリ・C・スピヴァクの議論が思い浮かびます。そこで語れるということは何なのか、語れる人ってどういう人なのか。そのうえで、出てくるものはどうあってもリアリティの一部でしかないし、いくらやっても足りないとわかっているが、ちょっとずつ掘り下げるしかない、という感じでしょうか。
堂目 確かに、社会問題の解決に取り組むと言ったとき、誰の声を聞くのかということは重要ですね。すでに出ている声だけでなく、語っていない人たちの声を拾うことが、社会課題に向き合う上で不可欠ですが、ここが一番難しい。何か方法論が確立できるでしょうか。
標葉 決定的な良いアプローチというよりは、注意すべき点については、これまでの学術の蓄積からある程度わかっていると思うんです。たとえばスピヴァクは、「語りを奪ってはいけない」という趣旨のことを言っています。記述者である研究者が権力勾配の中で、ヴァルネラブルな人たちの語りを奪うような形で代弁してはいけないという重要な規範です。そして、災害が起きた現場に研究者が大挙して押しかけ、データだけ取って帰っていくような、調査災害・調査公害は、まさに語りの収奪であり、ただの迷惑でもあり、いろんな意味で暴力的です。
また、先ほど堂目先生がおっしゃった、誰の声を聞いているのかをきちんと認識し、誰の視点や目線を通したものなのかを明らかにして、抑制的に書く必要がある。書くことによって、エンカレッジやエンパワメント、場合によってはアドボカシーが行われますが、それは誰に対するものなのかを意識して書かないと、新たなリスクやヴァルナラビリティを生むかもしれないことに注意しなければならないと思います。
ガイドランナーとして現場のそばで一緒に考える
堂目 標葉先生には、第4回ワークショップ「分断社会の超克~専門知をめぐる格差~」に、パネリストとグループディスカッションのモデレーターとして参加いただいきました。科学技術・イノベーションと人文学・社会科学の役割とも関連づけながら、今後の共創の場についてご意見をいただけますか。
標葉 ワークショップは、参加された方々の視点・論点が非常に多様かつ深くて、非常に楽しかったです。これをどう練り上げて次のより良い知識生産につなげていくのか、本当に多くの宿題をいただきました。私の問題意識である社会的なヴァルネラビリティの解消に引き付けながら、どのような知識生産の提案をしていくか。また、もう少しメタな問題として、その提案が社会的なインパクトを潜在的に持ち得るかを、いかに言語化しながら進められるのかが問われると思います。
ヴァルネラビリティの解消や語りの可能性を開くということは、結局、選択肢を増やすことと同義だと思うんですね。研究を通じて、具体的なアクションや政策的なオプション、あるいは視点や言葉の選択肢が増えていくこと。取れる手段や行動、言論が増えることが、ヴァルネラビリティをめぐる状況を少しずつマシにしていくはずです。知識生産とはまさしく選択肢を増やすような行為だということはもっともっと言っていいし、人文学、社会科学はそこで重要な役割を果たすと思います。
堂目 科学技術を開発する側の自然科学研究者と人文学・社会科学の研究者が共創する場では、誤解や分断が生まれることもあると思います。それは、どのようにしたら解消できると思われますか。
標葉 私自身、自然科学分野の研究者と一緒にプロジェクトを行うことが多いのですが、その際には、相手が守りたいものは何なのかを把握し、その人たちやコミュニティが大事にしたいと思っていることを出来る限り尊重します。こちら側だけで価値の問題を考えても意味がなくて、どういう言葉であれば互いに大事なものがうまく拾えるのか、そのような言葉や場を一緒につくっていくしかないと思っているんです。そのような関係構築には時間がかかりますが、時間をかけないと踏み込んだ議論にまではなっていかないと思います。
それは、科学研究の現場とそこにいる人たちのそばに、ずっと居続けるということでもあります。以前阪大の総長もされていた哲学者の鷲田清一さんが、現場のそば、臨床で額に汗して一緒に考えることが大事だという趣旨のことをどこかでおっしゃっていたように思うのですが、本当にその通りだと思います。ちゃんと近くに居てじっくり話し合いを続けること、それに足るだけのある種のコストやエフォートを、われわれ人文学・社会科学の側が払い続けられるかどうか。勝手なイメージですが、私は、視覚障害の方の陸上競技で一緒に走っていらっしゃるガイドランナーに近いイメージを抱いているんですね。アスリートのランナーがどんな走りをしたいのかを理解し、どう伴走すればいいのかを考える。無理に引っ張っても紐が切れて失格になるし、引きずられるだけでも良い成績は出ない。勿論一緒に走りきるだけの能力も必要となる。またその逆もしかりで、アスリートの方も、呼吸を合わせ、互いの専門性を理解し合いながら走るのが、一番記録が伸びるわけですよね。こういうガイドランナーのようなやり方を実地でやる人の数が足りていなかったことが、誤解や分断の要因の一つになっているとは言えるのではないでしょうか。

